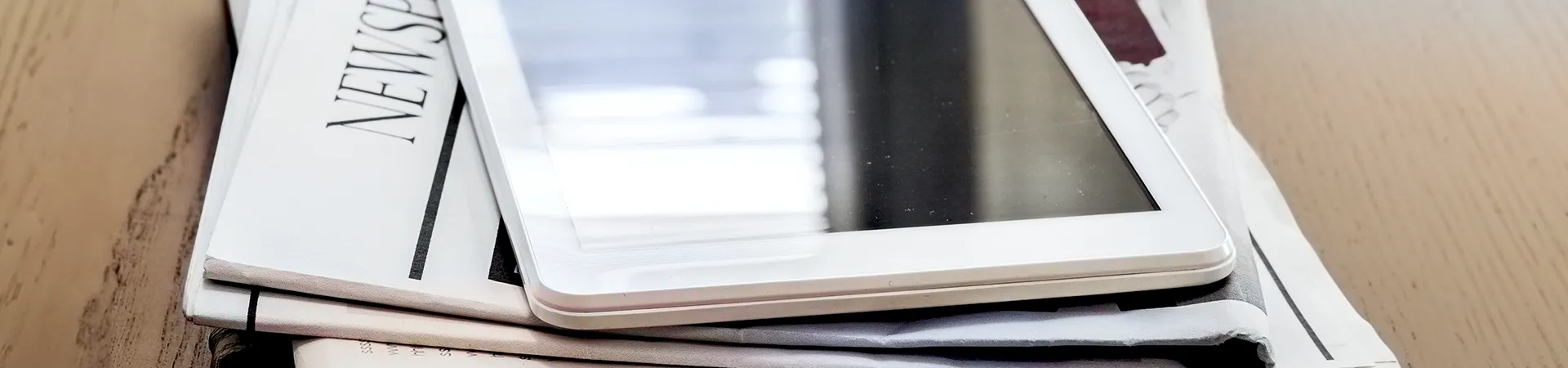
ニュースルーム
-

『ウィルキンソン タンサン シトラスビター』 7月9日発売
-

『WILKINSON GO テイスティマスカット』 6月11日発売
-

『アサヒ贅沢搾りプレミアム夏限定国産メロン』 5月28日発売 メロンの芳醇な甘みが広がる味わい
-

2024 年12月期 第1四半期 決算業績について
-

『アサヒスタイルフリー<生>』50万本を無料サンプリング
アサヒグループホールディングスについて
アサヒグループホールディングス株式会社は、ビールを中心とした酒類、飲料、食品で多様なブランドを世界で展開するリーディングカンパニーです。『期待を超えるおいしさ、楽しい生活文化の創造』をグループ理念のミッションとし、企業活動の根幹に据えています。
1889年に日本で創業して以来、数百年にわたる歴史と伝統をもった世界各地の醸造所やブランドをグループに統合し、絶え間ない革新に挑戦してきました。Asahi Super Dry、Peroni Nastro Azzurro、Kozel、Pilsner Urquell、Grolschといった独自価値をもつプレミアムビールをグローバルブランドとして展開しています。アサヒグループは、コーポレートステートメント「Make the world shine “おいしさと楽しさ”で、世界に輝きを」のもと、商品やサービスを通じて、人と人・自然・コミュニティ・社会とのつながりを生み出し、そのつながりで世界の今と明日を明るく輝かせることを約束しています。事業規模としては、年間100億リットルを超える酒類および飲料を世界中のお客さまに提供し、売上収益は2.7兆円を超えています。日本、欧州、オセアニア、東南アジアを中心に、世界各地で事業を展開する当社は、日本に本社を置き、東京証券取引所(プライム2502)に上場しています。





